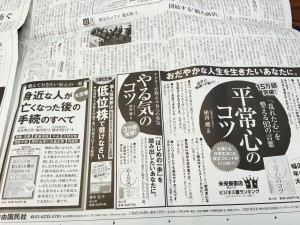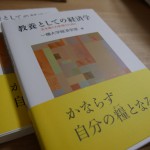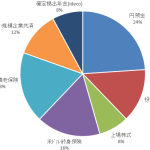今朝の日経新聞の、「マイナンバー始動 どう変わる」という記事では
マイナンバー導入のスケジュールやねらいなどが、解説されています。
※ 『身近な人が亡くなった後の手続のすべて』の広告も、掲載して頂いていました♪
11刷、累計5万部です。
10月には、国民の全員に郵送で通知カードが届き、マイナンバーが通知されます。
普通の方は、勤務先をはじめとした関係各所の指示に従い、
自分や家族の通知カードのコピーを提出すれば、とりあえずは大丈夫!
一方、大変なのは、個人番号関係事務実施者と呼ばれる
企業の総務経理担当者(や税理士事務所)です。
企業は、従業員や外部の専門家に支払う給与や報酬から、所得税を源泉徴収し税務署へ納めるため
他人のマイナンバーを数多く集め、手続きを行うわなければなりません。
でも、マイナンバーは、利用・提供・収集取得・保管・廃棄に、法律上、厳しい制限や罰則があり
中小企業を含むすべての企業が順守するのは、負担が大きいと危惧されているのです。
取り急ぎ、最初に手こずりそうなのは、やはり 「本人確認」でしょう。
マイナンバー法上の「本人確認」は、
従業員や外部の専門家などからマイナンバーを教えてもらう(通知カードのコピーをもらう)
「 ①番号確認 」だけではダメで、
その人が、「本当に」そのマイナンバーが付された人であるかの「 ②身元確認 」も
運転免許証やパスポートなど、写真つき身分証明書のコピーをもらうことにより、行わなければなりません。(既に届いた支払調書に、本人確認の概要につき記載がある出版社さんもありました)。
※ 採用した際、身元確認を行い済であるなど、 本人であることが明らかな場合「②身元確認」は不要
つまり、たとえば私なら
毎月顧問料を頂いている顧問先、原稿や本を執筆している出版社、講演を行った企業などのすべてに、
私の通知カードと運転免許証のコピーを渡すということに?
・・・マイナンバーを知らせるだけではなく、私が私であることの証明も必要だなんて\(◎o◎)/!
でも、仕事上の相手先すべてに、事務所の住所に加え、自宅の住所も明らかにし
さらに、職務上使用している通称に加え、戸籍上の名前も年齢も明らかにすべきとなれば
嫌がる人も多いはず。
この本人確認手続を企業に求めるのは、ちょっとハードルが高いと感じます。
実際に、私が顧問先でマイナンバーの研修会を行った際にも
(その会社は、かなりの人数のフリーランスの方に報酬を支払っているため)
「果たして全員に、マイナンバー制度の説明をして、本人確認が行えるでしょうか」という不安の声があり、
また先日、日本税務会計学会の月次研究会で、青木丈先生のマイナンバーの研修に出席した際にも、
税理士の先生方から同様の質問が出ていました。
原則的な本人確認方法が困難な場合には、例外的な方法も認められているとはいえ
専門家は、専門家向け情報の公表を、注意深く追う必要がありそうです。
**********
たまたま 「NHKスペシャル 明治神宮不思議の森 100年の大実験」を見て、ふと思い立ち
カメラ片手に、明治神宮御苑を散策してきました。

表参道や代々木近辺に行く機会は多いのですが、明治神宮を訪れたのは多分二十年ぶりくらい。
近すぎると、逆に行かないものですね。
自然の緑と水に癒され、夫婦になったばかりの幸せそうなお二人にも遭遇。

こんなおだやかな日々が続くよう、神様にお祈りしてきました。