先週やっと、日本税務会計学会 月次研究会での発表が終わりました。
テーマは、相続税申告の際よく遭遇し、そして悩む「賃貸アパートの空室部分をどう評価するか?」です。
ここ数か月間ずっと、実務の合間や夜に準備をするのは、時間的に厳しく
そして精神的にもプレッシャーが大きく、大変でした…
でも、2月は繁忙期であり参加者は少ないと思っていたのに
数多くの先生方が足を運んで下さり、質疑応答の時間にもたくさんの有益なアドバイスを頂き、
感謝の気持ちでいっぱいです。
藤曲先生や訴訟部門のみなさまを始め、諸先生方、どうもありがとうございました。
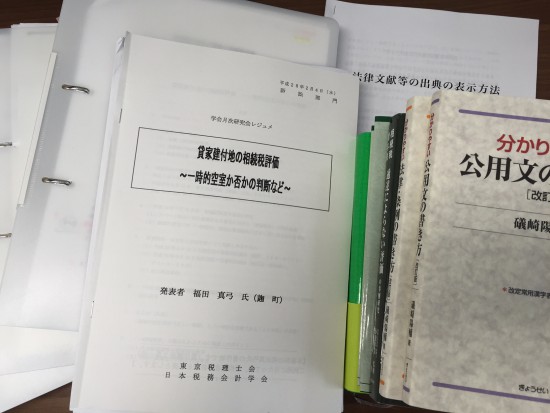
貸家建付地の相続税評価とは
「貸家建付地」とは、賃貸マンションや賃貸アパートの敷地のことで
自宅や駐車場として使っている土地より、相続税の計算上は低く評価できます。
アパートに住む借家人は、借地借家法上、「借家権」という強力な権利を持っていて
貸主の都合では退去してもらえず、地主は土地の使用収益が制限されることをを斟酌したものです。
【 財産評価基本通達26 貸家建付地の評価 】に基づき
自用地としての評価額 ― (自用地としての評価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
で求めます。
※「賃貸割合」とは?
アパートの空室部分には、借家権がないと考えられるため
「賃貸割合」(実際に貸している部分の床面積/全体の床面積)をかけ、実際に貸している部分だけ評価減する。
ただし!賃貸割合の計算上、
継続的に賃貸していた部分で相続時に一時的に空室だった部分は、賃貸していたとして構わない
ことになっています。
「継続的賃貸における一時的空室」か否かはどう判断する?
上記は、平成11年に財産評価基本通達が改正され、考え方が確定したものですが
最近は、課税庁と納税者の間で、中でも以下の例示の(3)につき、意見の相違が生じています。
国税庁タックスアンサー No.4614 貸家建付地の評価
また、継続的に賃貸されていたアパート等の各独立部分で、例えば、次のような事実関係から、アパート等の各独立部分の一部が課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において一時的に空室となっていたに過ぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして差し支えありません。
(1) 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。
(2) 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。
(3) 空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。
(4) 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。
もともとの通達の制定趣旨は
「賃貸アパートに一人でも借家人がいれば、敷地全体にその借家人の権利が及び、土地の減価要因になる。
だから、継続的に賃貸業を行っているなら、空室部分にも評価減を認めてあげようね」という考え方です。
よって、空室期間が何か月以上はダメという形式的な基準はないにも関わらず、
近年の国税不服審判所の裁決では、法令でも通達でもない、タックスアンサー上の例示=たとえを根拠に
「1か月を超えたら(継続的賃貸における一時的空室とは)認めない!」という指摘が増えているのです。
旧賃借人の退去から新賃借人の入居までの期間が1か月であることなど、ほとんどないにも関わらず…
「財産評価基本通達逐条解説」の解説部分の削除・書換え
従来、財産評価基本通達の解説書(逐条解説)には、 前述の通達の制定趣旨
(賃貸アパートに一人でも借家人がいれば~)の内容が、きちんと書かれていました。
しかし、平成22年版からは、その部分がザックリ削除され、一部書換えられてしまっています。
※ 削除された文章
「しかし、アパート等に現に借家人が存在している場合には、その借家人の有する権利は
敷地全体に及ぶと考えられることから、このような一部に空室のあるアパート等については、
入居者のいないアパートや一戸建ての貸家と異なり、
借家人の存在がその敷地全体の価格形成において相当の減価要因となり得る場合もある。」
※ 書き換えられた文章
「このように継続的に賃貸の用に供されているような場合について」
↓
「このような空室が一時的に生じているような場合についても」
課税庁が考え方自体を変えたのか否かは不明です。
でも、裁決事例やこの削除・書換えから見て
課税庁は、通達の制定時と比較し、貸家建付地の範囲を狭めようとしているように(私には)思えました。
**********
税理士は、評論家ではなく実務家ですから、実際にお客様の相続税の申告を行う際、
自分自身で判断し、 お客様の納税額を確定させなければならない責任を負っています。
そこで発表では、私ならどう理論付けをし、税務署に事実認定してもらうかにつき
(稚拙ですが)自分なりの考えをまとめ、発表しました。
最近はまた、相続税対策としてアパート建築を提案する不動産会社さんも増えているようなので
ぜひこういった税務上の動向も知った上で、有益なアドバイスをしてくれたらいいなあ~と思います。
















