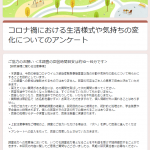日本家族心理学会の、多世代家族療法の研修を受講しました。

日本家族心理学会の研修
日本家族心理学会は、
家族心理学の研究を推進し、家族支援の技法向上を図る目的の学会です。
「心理の専門家」の学会ですが
家族支援の理論や技法は、
相続業務で家族と関わる際に応用できる点が多いです。
年6回、家族支援に関する研修が行われていて
私は今回、かねてから一番興味のあった、多世代家族療法の研修を受けました。
講師は野末武義先生でしたが、ものすごく分かりやすくて感動。
税理士なら武田秀和先生的な感じでしょうか。
大御所なのに、実務的でざっくばらんで。
ウェブ開催でしたが、ライブ参加できたので
Zoomのブレークアウトルームで
様々な職業の参加者の方々と意見交換できたのもよかったです。
ディスカッションのテーマは不登校児の家族面談。
でも、相続時の家族会議にも応用できる内容だと感じました。
家族療法とは
一般的に、心理的な支援は
「個人」に対して行われることが多いですが
家族療法は、個人ではなく「家族」をひとまとまりと考え
家族全体にアプローチし、問題の緩和を図る支援方法です。
家族療法にはいろいろなモデルがあり
そのベースには、家族システム理論があります。
それは、たとえば
不登校や引きこもり、摂食といった「個人」に生じている問題も
その個人が原因というわけではなく
夫婦や親子、きょうだいといった家族内のサブシステムや
そのサブシステムから成る家族システム全体の
不十分さや相互影響から生じている側面があるからです。
家族療法もその前提で、家族をサポートしていきます。
多世代家族療法と相続業務が似ている点
野末先生によれば、
多世代家族療法は家族療法の中でも
日本の家族を理解するのに最も適した理論だとのこと。
なぜなら、多世代家族療法は、
家族を3世代以上でとらえて
その影響が世代間伝達していると考えるからです。
私が多世代家族療法を初めて学んだのは大学院の講義で、でしたが
ジェノグラムという
3世代以上の家族を図式化したものを使って援助をする点が
税理士が、被相続人(父母)と相続人(子)だけでなく
祖父母や、子の配偶者や孫の有無
そして、その情報も家系図に書き込んで、
ヒアリングしつつ問題点や解決策を考えるやり方と、よく似ていると感じた記憶があります。
きっと日本の「イエ」制度と親和性が高いのか…
多世代家族療法を学んだおかげというか
その特徴である
・親の源家族における体験(親もかつては、誰かの子どもや誰かときょうだいだった点)
・各個人の源家族からの自己分化の程度(家族から精神的に自立している度合い)
をより気にかけながら、お客様に対処できるようになりました。
当然ですが、自分の家族もその視点で見られるようになるという、副次的効果もありました。