「人は誰でも、ある日突然支えられる存在になる。
それまで無意識のうちに、仕事をし家庭を営む自分を支える側だと思っていたが、その状況は一瞬で変わった」
数か月前、日経新聞の夕刊で目にした、元厚労事務次官の村木厚子さんの言葉です。
東京税理士会の後見人研修
先日、終日丸3日、税理士会の「成年後見人等養成研修」に参加しました。
この研修後、修了審査を通ると、税理士会が年に1度家庭裁判所へ提出する、成年後見人の推薦者名簿に登載されます。
主として相続案件を多く受任している私の場合、依頼者は、お年を召された個人の方が大半です。
被相続人や相続人が意思能力のない被後見人や被補助人、被保佐人(サポートされる側)とか、
相談者が任意後見を検討中とか、後見人(サポートする側)である家族の財産使い込みや虐待の話などが多くあるとか・・・
後見は、業務と切っても切り離せず、そして、馴染みやすく取り組みやすい分野です。
相続は「死後、財産を誰にどう分け、税金をいくら払うか」の話です。
とはいえ、「高齢期~亡くなるまで~死後」の財産や家族の話は、一体で考えるのが普通。
そのため相続案件は、故人の生前の家族関係、お金、医療介護などの状況に大きく左右されます。
今回の研修は、学者、弁護士、司法書士、医師、社会福祉士、家庭裁判所の書記官など各方面の専門家から、
実務の苦労話、制度の問題点、海外との比較、今後のあるべき姿などを聞き、心を大きく動かされた3日間でした。

税理士と後見業務
税理士は、当然に専門職の立場で後見人となれる弁護士や司法書士と違い、
税理士資格では後見開始の申し立てすらできないため、他の専門家と協力しながらのサポートが中心になります。
ただし最近は、親族後見人や倫理観に欠ける一部の専門職後見人による財産の使い込みが増えているため、
家庭裁判所が後見監督人(サポートする人を監督する人)を選任するケースが増えているそうです。
監督人の仕事は、後見人が収支と財産管理をきっちり記録し、問題ないよう遂行しているかをチェックすること。
これはおそらく、他の士業と比較した税理士の一番の得意分野です。
(何せ常に税務署の厳しいチェックを受けていますから)
それに、細かな数字は苦手という他士業の方も、意外にいらっしゃるようです。
きちんと、民法や社会保障の分野の勉強をすれば、税理士は監督人に適任かもしれません。
専門職後見人の数はどんどん足りなくなっていますので、
「親族後見人や市民後見人+後見監督人」の組み合わせの際、多くのサポートができそうです。
自分自身が全分野に詳しくはなれなくても、誰に相談し、どこに頼めばいいか、
つなぎ先を見つける道案内くらいは、できるようになりたいと考えています。
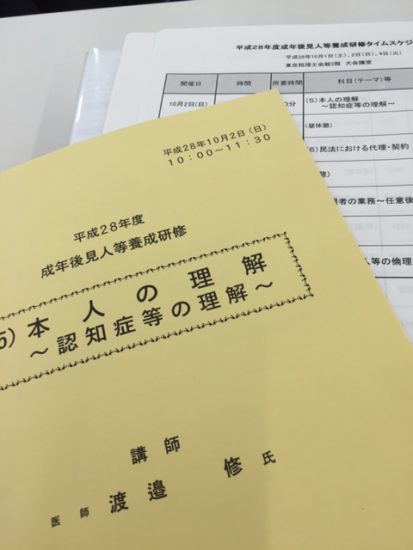
赤の他人の人生に寄り添う
後見人の業務は「療養看護と財産管理」です。
簡単に言えば、自分で自分の命や健康、財産を守り使うことができなくなったとき、普通の人ひとりひとりの生活を守るための、法的なキーパーソン。
財布の中身を考え、日々の生活を支える計画を立て、契約し、お金を払い、実行されるのを監視します。
村木さんの記事の最後の一文には
「人は支えがなければ生きていけない、しかし支えらえるだけでは元気が出ない。
誰もが支え手となれる、そして誰もが必要な時に支えてもらえる社会を目指したい」とありました。
この切り抜きを手帳に入れ、私には何ができるんだろうと、たまにぼんやり考え、取り出し眺めています。
















