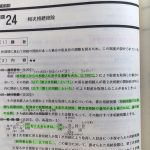おとといの新聞に「生前贈与手続、無料で代行 三菱UFJ信託」という記事がありました。
教育資金贈与信託の手数料も無料でしたが、こちらも無料だとのこと。
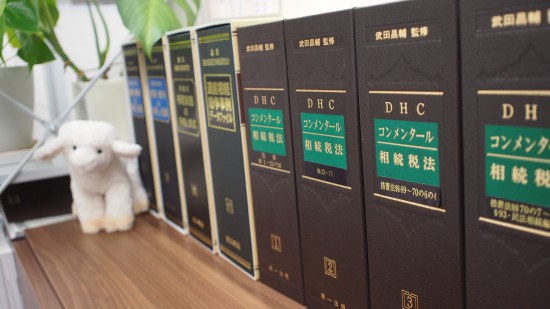
信託銀行の暦年贈与信託サービスが無料の理由
銀行業務はボランティアではありません。
暦年贈与信託サービスを無料で提供できるのは
セットで遺言信託(公正証書遺言の証人立会い+遺言書の保管+財産の名義書換)サービスも勧めれば
利益を得られるからです。
業務の手間や難易度と比較して、信託銀行の遺言執行報酬はあまりに高すぎますが
公正証書遺言を作り、第三者を遺言執行者に指定し、名義書換をお願いすること自体は
安心につながりますから、キャッシュに余裕があるなら、そのお勧めに乗ってもよいと思います。
ですが、どうせ信託銀行に頼むなら、遺言信託より先に
遺言代用信託を利用すべきでは?と感じる機会が増えています。
信託銀行にキャッシュを預け、自分の生前は自分が毎月一定額のキャッシュを受け取り、自分の死亡時に残りがあれば、親族が一時金または毎月定額で受け取れるという商品
相続対策より生前の使い込み対策の方が先
平均で週に1、2回、単発での税務相談を受けますが、
認知症で意思能力が不十分になった人の財産を、親族が使い込んだというご相談が続きました。
たとえば
「父の相続時、認知症の母の代わりに、子が勝手に遺産分割協議で母の取り分を決め
母が相続した (はずの)財産を、子が使い込んでいる」
「叔母は元気なとき、甥と任意後見契約を結んでいたが
今は叔母が認知症になり、意思能力がなくなっているにも関わらず
甥は監督人の選任を家庭裁判所に申し立てず、叔母の財産を勝手に使っている」
「認知症の母の介護にお金がかかると、自分が相続する財産が減るので、と
子が母の預金から介護費用を出すことを渋る」
などです。
本来、家裁の手続きを経て成年後見人がつけば、後見人が本人の代理として法律行為を行います。
または、事前に信頼できる人と任意後見契約を結んでいたら
意思能力がなくなった時点で、後見人が監督人の選任を家裁に申し立て
同じく本人をサポートする手はずを整えてくれるはず。
親族による使い込みが起きるのは、これらの制度を利用していない場合のはずですが
実際には、利用しているのに制度が機能していないのです。
後見業務を専門としている司法書士さんに相談したところ
後見人は、本人の資金収支について家裁に報告書は出すものの、詳細は明らかする必要がなく
「雑費5万円」のような超ザックリした記載でもOKだとのこと。
税理士的には衝撃ですが。
なので、親族後見人ではなく、弁護士や司法書士などの専門家でも、使い込みの事例はあり。
それじゃ、「認知症の人のお金は使い込んでもOKだよ(バレないよ)」って言っているようなもの?
十分なお金があり、信頼できる家族がいても
体が不自由になり、意思能力がなくなったときに、自分のお金を自分のために使ってもらうには
親族や専門家より、銀行の遺言代用信託の方が安心に思えるのです。
お金を使い込まれるリスクが低く、毎月決まった金額を安心して受け取れるので
三菱UFJ信託銀行の「ずっと安心信託」という商品名にも納得です。
相続のご相談を受けながら
自分の死後(相続)の対策より、生前(老後資金)の対策の方が先だと実感するのは
何だか悲しい気持ちになります。