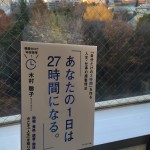知りたいことがあったら、とりあえずネットでググりますが
ヒットした情報が信頼できるのか、悩むことがあります。
ヘルスリテラシーの本を読んだら、健康情報の信頼性の見極め方として
「か・ち・も・な・い」というひらがな5文字が紹介されていました。
マネー情報の取捨選択にも役立ちそうです。
目次
か・ち・も・な・い
「か・ち・も・な・い」は、
その情報が信頼できるか判断するときの、チェックポイントの頭文字です。
か:書いた人は誰か
その情報を発信しているのは誰か。
実名か匿名か
専門家か素人か
専門家なら、所属や資格が書かれているか、など。
責任の所在が明らかな方が、信頼性が高いと考えられます。
ち:違う情報と比べたか
情報源が1つでは、必要な情報をカバーしきれていない可能性があります。
メリットだけで、デメリットが書かれていない、とか
個別論点だけで、全体像が見えない、とか。
どちらも、両方から判断できた方が安心できます。
も:元ネタは何か
ちゃんとしたエビデンス(根拠)のある情報か。
意見や感想、体験談は、あくまで私見ですから
私はこれで治ったとか、これで儲かった、とかではなく
効果が検証済の研究や論文がある、
法律の条文や、実際の運用成績が示されているなどの、元ネタを確認します。
ネットショッピングのためにググるなら
口コミの方が、むしろリアル意見として参考になるんですけどね。
な:なんのための情報か
記事の目的は。
広告や、何かを売るために書かれたものではないか。
新聞や雑誌でも、記事っぽいけれど
「広告」「PR」の文字が小さく入っているという紙面をよく見かけます。
また、民間企業、特に大企業のサイトは
普通の方向けのやさしい言葉で書かれていて、分かりやすいですが
そもそも、情報提供の目的が「自社の製品やサービスを買わせるため」なので
偏っていることを念頭に置いて読む必要があります。
役所など公的機関のサイトは、専門用語が多く読みにくいですが
それは正確性を期したり、中立性を保ったりするためであり。
「なんのために」その情報が書かれているか、という視点
私はこれが一番重要じゃないかな、と思っています。
い:いつの情報か
作成日や更新日が記載されているか。
医学の進歩が日進月歩であるのと同じように
マネーの情報も、経済情勢や法改正の影響を大きく受けます。
もし新しい情報だけを調べたいときは
Googleのボックス右下にある「ツール」をクリックすると
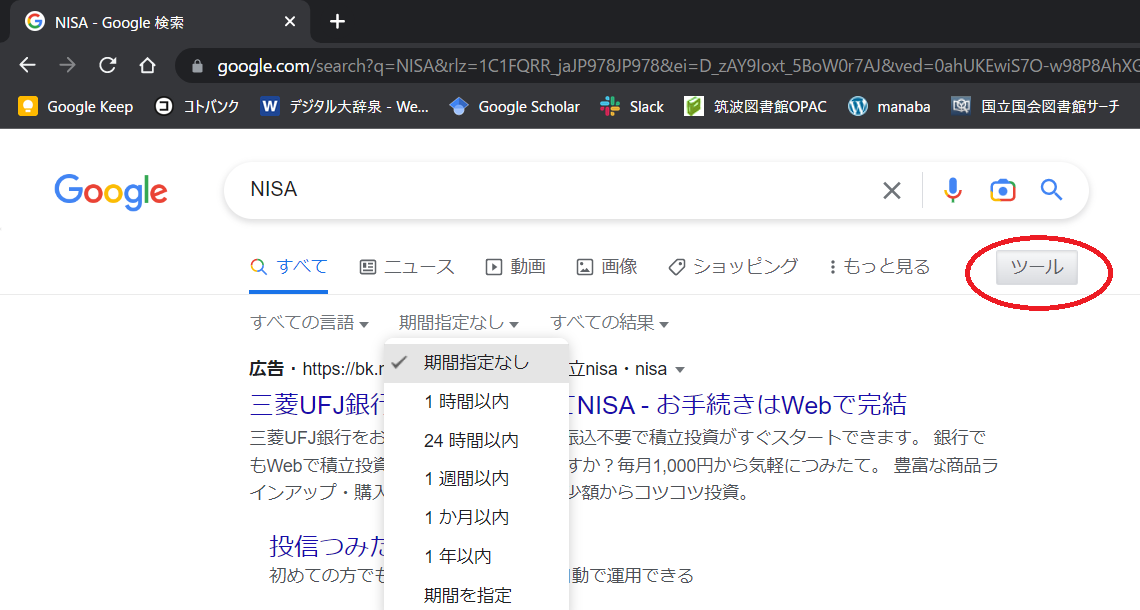
通常は「期間指定なし」の情報が出ますが、新しい情報だけに絞って検索もできます。
情報を得た後、どうするかがリテラシー
医療の情報は過去に、「WELQ」というまとめサイト
(素人ライターが不正確な記事を大量に書き、情報量の多さでアクセス数を集めていた)問題があり、
上記のチェックポイントが重視されているようです。
一方、マネーの情報も
iDeCoは昨年の制度改正で、新規加入者数がかなり増えたそうですし
NISAは、令和5年度の税制改正で非課税枠等が大幅に拡大されるので
金融機関主導のやや偏った情報が、今後広まりそうです。
ただ私は、「か・ち・も・な・い」に気をつけ、信頼できる情報を入手することも大切だけど
情報はあくまで情報で、誰でも手に入れられるので
それをベースに自分がどう判断・意思決定し、行動するかがリテラシーだと思うんですよね。
iDeCoやNISAの活用もそうですが。
なので、ネット情報はもう玉石混交だからと割り切り
ググってあたりをつけた後は、それを鵜呑みにせず
・本を2,3冊読む
・周囲の人に体験談を聞く
・詳しそうな専門家に相談に行く
といった自分なりの行動ができれば、リテラシーとして十分なのでは、と考えています。