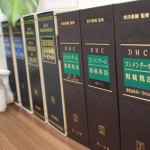「相続登記」とは、相続した不動産の名義を変えること。
この相続登記が、2024(令和6)年4月1日から義務化されます。
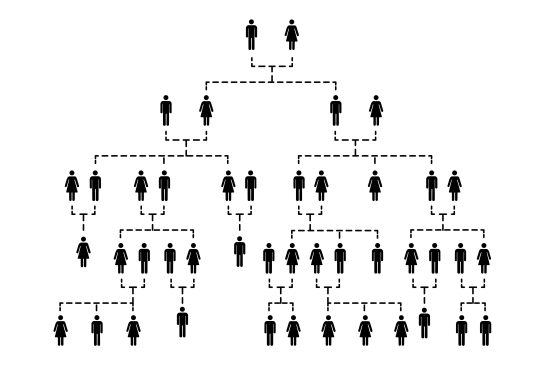
相続登記とは
不動産の名義変更手続きは
登記簿(登記事項証明書)上の所有者名を、変更することにより行います。
具体的には、法務局に「所有権の移転登記」を申請する手続きが必要です。
この申請手続きのことを、一般的に「相続登記」と呼んでいます。
相続登記が義務化された理由
ただ現在は、相続登記は義務ではありません。
登録免許税や司法書士報酬などがかかるため、相続登記をしないケースもよくあります。
また、遺産分割をしないまま、次の相続やその次の相続が発生し
共有者がねずみ算式に増えてしまうことも、めずらしくありませんでした。
こういった所有者のわからない土地が
公共事業や災害復興事業、民間の土地活用の妨げになっているという指摘があり。
今後高齢化が進むにつれ、さらに所有者の不明な土地が増えないよう
新たに相続登記が義務化されることになりました。
いつから?
相続登記の義務化は、2024(令和6)年4月1日から始まります。
それ以後は、不動産を取得した相続人は
取得を知った日から3年以内の相続登記申請が義務化され
正当な理由なく相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科されます。
気をつけたいのは、2024(令和6)年4月1日「以後」の相続だけではなく
それより前に発生した、過去の相続も義務化の対象になる点です。
なお、過去の相続は、相続日から3年以内ではなく
法の施行日である2024(令和6)年4月1日から3年以内の相続登記が義務になります。
まとめ
以上、新たに始まる、相続登記の義務化について書きました。
さらに今後は
・ 住所変更登記の義務化
(法改正済。開始時期は未定。2026(令和8)年4月までに義務化開始の予定)
・ 相続土地国庫帰属制度の創設
(相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度。2023(令和5)年4月27日開始)
など、不動産関係の改正が続きます。
該当する不動産のある方は、早めに司法書士さんへ相談することをおすすめします。
お客様に誘われ、アオイのセールへ。
事務所から徒歩2分の場所に、東京支社があることを初めて知りました。
HERNO以外のブランドはそこまで混んでいませんでしたが
セールは苦手なので薄手のコートとざっくりニットを買い、早めに退散しました。