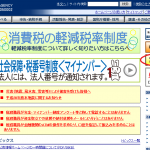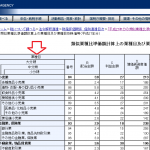今朝の日経新聞に 「住宅資金贈与の優遇拡大、国交省、非課税3,000万円枠」 という記事がありました。
両親や祖父母からマイホームの購入資金を贈与してもらうなら、 今年中なら、省エネ住宅は1,000万円まで
その他の住宅は500万円まで、贈与税が非課税になる特例があります。
相続税の「生前贈与加算」の対象にもならないため、 贈与税・相続税共にかからず、かなりお得です。
※「生前贈与加算」・・・あげた人が亡くなる前3年以内にした贈与は、相続税の課税対象になるという規定
国交省は、今年いっぱいで期限が切れるこの特例を、来年以降も延長し、さらに非課税枠を
省エネ住宅は上限3,000万円、その他の住宅は2,500万円に拡大したいとのこと。
**********
節税だけを考えるなら、 この税務上の特例を使い
「子が払う贈与税」と「親の財産にかかる相続税」の軽減を図るのが一番です。
でも、民法上、生前贈与は相続の際に特別受益(=遺産の先取り)として扱われ
相続時の子の取り分は、贈与を受けた分だけ減ってしまいます。
「それは避けたいけれど、頭金として出せる額(と住宅ローンで借りられる額)以上の物件を買いたい」なら
贈与ではなく、借入という形をとることも可能です。
ただ、ありがちなのは、借用書は作ったものの、「出世払い」や「あるとき払いの催促なし」というケース・・・
それって、第三者間だったら絶対ありえない!(>_<) ので
税務署から「親からの借入ではなく、実際には贈与だ」と指摘されてしまいます。
そこで注意すべきポイントは、以下の3つ。
できるだけ、第三者間でお金の貸し借りをするときと、違いすぎないよう心がければOKです。
・ 必ず、「金銭消費貸借契約書」を作る
返済期間(○年)、返済期日・返済方法(毎月○日に銀行振込で、など)、毎回の返済額(○万円)、
利率(年利○%)などの返済条件をキチンと記載し、両者が署名押印し、印紙を貼り、消印すること。
親の余命や子の年収を考慮して、返済期間や毎月の返済額が、現実的に可能な期間・金額でないとダメ!
・ 必ず、現金手渡しではなく銀行振込で返済する
実際に、ちゃんと返済しているという事実が一番大切なので、必ず銀行振込で返済すること。
・ できれば、利息を払う
「無利息貸付=即贈与」ではありませんが( ※相続税基本通達 9-10 無利子の金銭貸与等 ただし書き)
できれば、通常の住宅ローン程度の金利(1~2%)は付すのが理想的。
親が受取った利息(雑所得)には、所得税がかかります。ただし、親がサラリーマンや年400万円以下の年金受給者の場合には、利息相当額が年20万円以下なら申告不要になり、結果的に親には課税なし!
やむを得ず無利息で借りたなら、利息相当額は、親から子への贈与だとみなされますが、その分が年110万円以下なら、贈与税の非課税枠内なので、子は納税なし!
借入金そのものにつき贈与だと言われないためには、上記通達のただし書き
利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、
強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとするに該当するかどうかがポイントです。
相続時の取り分は減らしたくないけど援助してほしいなら、無利息で借りる選択肢もありですね(^_^)/